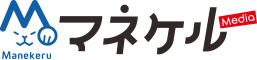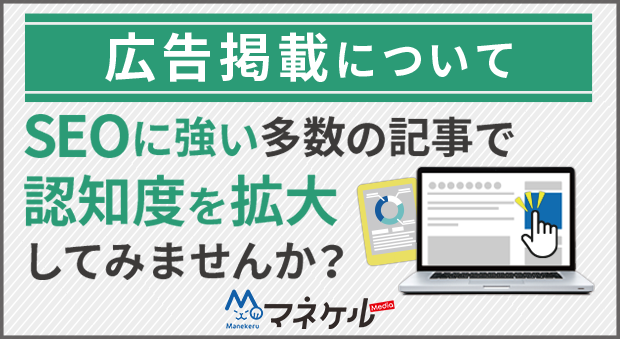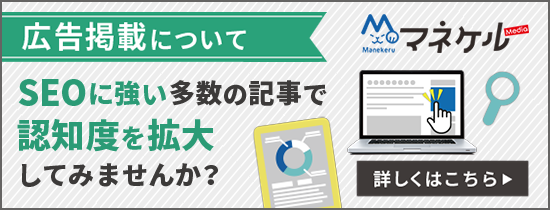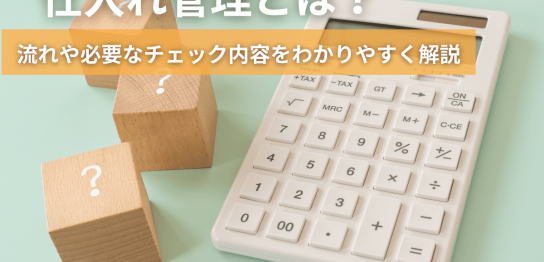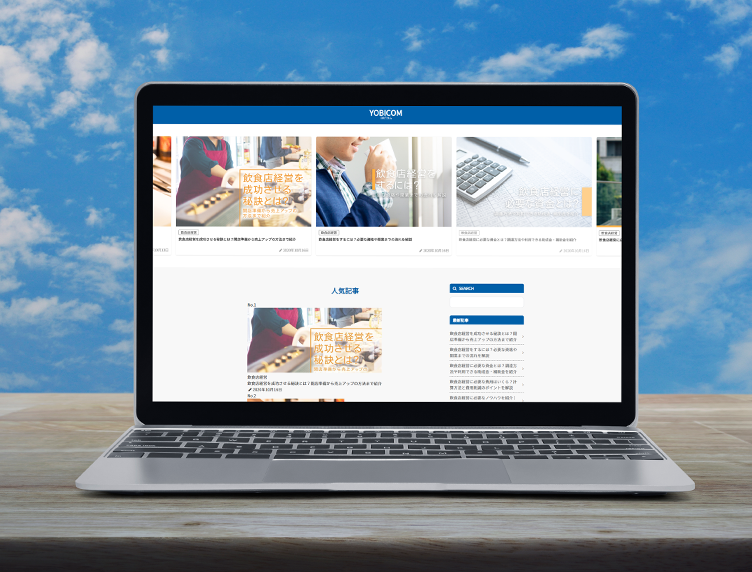パン屋を開業したいと考えていても、知識や経験が無く何をしなければならないのか分からない、という方もいるのではないでしょうか。自分の理想とするパン屋を開業するためには、どのような手続きがあり何が必要となるのか、しっかりと把握した上で準備を進めることが重要です。
今回は、パン屋開業までに必要な費用や資格、開業までの一連の流れを紹介します。
パン屋の開業・経営にまつわる基礎知識

パン屋というと、焼いたパンを並べて販売するというイメージのみを持つ人もいるかもしれませんが、世の中の変化や多様化もあり、パン屋の経営は複雑化しています。ここでは、パン屋の開業と経営に関する基礎知識とメリット・デメリットを紹介します。
パン屋の具体的な業務内容
パン屋における基本的なサービスは「パンの製造」「パンの販売」です。業務内容についてはパン屋の運営形態によって異なります。
まず「製造」の工程では材料を仕入れるところから始まり、仕込みや生地の成型、焼き上げなど、パンを作る業務が主となります。他にも、袋詰めの作業や一緒に販売する飲み物などの準備も行います。店舗の規模によって、1人ですべて行う場合もあれば、分担して行うこともあります。
そして「販売」の工程では、出来上がったパンを店内に陳列・補充し、接客対応やレジ業務を行うことになります。持ち帰りだけでなく店内に飲食スペースを設けているお店であれば、注文の受付や対応、席の清掃、食器の洗浄などの業務も加わります。また、焼いたパンをそのまま店舗で販売するのではなく、レストランや他の販売店に卸売という形で販売するケースもあります。
さらに、製造や販売だけでなく、各工程に加えて在庫管理や売上管理、集客対策などの店舗運営に必要な業務もあります。よって、店舗の大きさや販売商品数などの規模感、その時々の経営状況などによって、必要な業務やスタッフの数は異なります。
パン屋事業のニーズは?
株式会社矢野経済研究所の「パン市場に関する調査を実施(2023年)」によると、国内パン市場規模は2020年度の情勢変化などによって一度減少したものの、現在は回復傾向にあります。2019年度の市場規模1兆5,786億円に対し、2020年度は1兆5,196億円となっていますが、2024年度は1兆5,857億円が見込まれています。
2020年度は、情勢の変化によってパン屋だけでなく多くの外食産業が打撃を受けていましたが、規制緩和などにより徐々に人々の暮らしや経済活動が戻るにつれて、需要も回復しているといえます。2021年度にはマリトッツォやフルーツサンドなどの流行などがあったこともパン市場の需要回復に影響していると思われます。
一方で、昨今の原材料高騰による影響で値上げが必要になった事業者も多くあり、今後の消費者行動への影響も考えられます。現状市場は微増を続けていますが、付加価値のある高級パンを好む消費者や、値上げに関わらず従来品を求める消費者、値上げを原因に離反する消費者など、ニーズがより分かれている傾向もあります。よって、提供する商品の価値や価格、消費者行動などの関係性によるニーズをうまく把握することが求められるでしょう。
参考:パン市場に関する調査を実施(2023年) | ニュース・トピックス | 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所
パン屋を開業する方法
パン屋を開業する方法としては主に次の3つがあります。
- 独立開業
- フランチャイズ開業
- 支援・サポートを受けての開業
自分の理想の経営方法や販売方法にあわせて検討してみましょう。
パン屋の開業方法1:独立開業
独立開業とは、他のパン屋などでパン製造の技術や経営方法について知識を深め、その後独立して自店を開業するという流れです。
自分が理想とするパン屋を持つということや、自分の思う通りに運営を進められるという点で、独立開業は様々な事に挑戦出来る可能性があります。しかし、開業手続きや仕入れルートの開拓、商品開発や製造技術向上などをすべて自力で行わなければならないため、時間やコストがかかるという認識が必要でしょう。
パン屋の開業方法2:フランチャイズ開業
フランチャイズとは、親企業に加盟しロイヤリティを支払うことで、看板を使用する権利や商品を販売する権利、経営ノウハウなどを得ることができる仕組みをさします。
フランチャイズ開業の一番のメリットは、未経験であってもパン屋を開業することができるということです。自力で開業する場合はさまざまなことを自力で行わなければならないため、開業への資金準備が必要ですが、フランチャイズ開業の場合、比較的安価な資金で開業できるだけでなく親企業からのサポートが受けられます。また、親企業の知名度が大きい場合、その看板を使用できるということもメリットといえます。
ただし、毎月のロイヤリティや加盟料の支払いが必要になるほか、パン製造や営業時間などはマニュアルに従わなければならない部分が多いため、自由度が低いというのはデメリットといえるでしょう。メリットだけを見ると開業が簡単そうに思えますが、加盟料を支払ったあとで「想像と違った」ということもゼロとは言えないため、さまざまな情報を自分自身で集めながら慎重に検討してみましょう。
フランチャイズについては、こちらの記事で概要や加盟するメリット、選び方などを紹介しています。
パン屋の開業方法3:支援・サポートを受けての開業
パン屋開業を目指す人のために、フランチャイズ開業という形ではなく開業支援としてサポートする業態もあります。フランチャイズ開業とは違ってロイヤリティが発生せず、自分が支援してほしいという部分だけをサポートしてくれるため、自由度は大きいです。
一方で、開業支援としてどのようなサポートが得られるのかを具体的に把握しておかなければ、期待する支援を思うように受けられなかったり、支援の内容が地域に見合わないものであったりするため事前の確認が必要です。また、ロイヤリティが発生しない代わりに契約金が必要となるので、金額面の確認も必要でしょう。
パン屋を開業するまでの流れ

パン屋の開業を決意したあとは、開業までの具体的な流れを知る必要があります。技術面や店舗に関すること以外にも、さまざまな手続きや資金の確保など複雑なことが多く、パン屋開業をスムーズに進めるためにも事前に確認しておきましょう。
パン作りの技術を習得する
パン屋を開業する以上は、自分自身がパン製造の技術を身につける必要があります。技術の習得には、調理関係の専門学校で学ぶ方法もあれば、別のパン屋に勤務して技術を身につける方法などさまざまありますが、安定したパン製造技術を手に入れるには年単位での長い時間がかかる可能性があることも理解しておきましょう。そのため、パン屋開業までの年数を逆算して計画的に進めることもポイントです。
店舗のコンセプトを明確にする
パン屋開業に必須なもののひとつが店舗のコンセプトの明確化です。コンセプトとは、パン屋開業にあたっての軸となるものであり、運営していく方向性をさします。
「国産小麦にこだわった手作りパン」「あらゆる年代が毎日食べられる地域密着型のパン屋」「食事としてだけでなくスイーツ感覚でも楽しめるパン」など、基本軸を明確にしておくことで、今後の構想やメニュー作りなどをブレることなく決めていくことができます。
自分の理想に近いパン屋をリサーチして、コンセプトと照らしあわせていくのも良いでしょう。
パン屋のコンセプトの決め方についてはこちらの記事も参考にしてみてください。
パン屋の定休日や営業時間を決める
パン屋にとって、営業時間と定休日をいつにするかは集客に影響する大きな要素の1つです。地域や立地によって、人の集まりやすい時間や曜日は異なるため、自分の店舗に適した営業日時を考えることが大切です。
例えば、「学生の下校時間や社会人の退勤時間にあわせて、駅前の昼過ぎから夕方以降を狙う」「平日の火曜日は特に人通りが少ないので定休日にする」などの方法が考えられます。
できる限り店舗を取りまく環境や人の動きを把握して、具体的な集客のイメージができるようにスケジュールを計画しましょう。
パン屋開業に必要な費用・資金調達をする
パン屋開業までに必要な費用は、数百万から一千万円程度が考えられます。物件についてはどのくらいの規模のパン屋を予定しているかにもよりますが、必要となる店舗物件の敷金・礼金を踏まえると安くても50万円、利便性が良いなどの立地によっては高くなると数百万かかります。物件が決まっても内装・外装工事や、什器や製造機器などの設備費用も必要です。さらにフランチャイズ開業や支援・サポートを受けての開業を目指す場合には加盟料や契約金もかかります。
また、パン屋の場合、店舗の内装にこだわりたい人も多いかと思いますが、内装のデザインによっても必要な費用が変動します。パン屋の内装デザインにかかる費用やポイントは以下の記事で解説しているので、あわせて確認してみてください。
少しでも初期費用を抑えたいのであれば、前の店舗の装備がそのまま残ったままの居抜き物件を探したり、製造機器などのリース会社を探したりする手も考えられます。少しでも好条件が見つかるように、さまざまな情報を集めてみましょう。居抜き物件についても、こちらの記事で詳しく解説しています。
参考:パン屋の開業に必要な資金・資格・法的手続きについて | リライブフードアカデミー | 開業・就職 カフェ・パン・パティシエの専門スクール・学校 リライブフードアカデミー
各パン屋の開業に必要な資格や手続きを取得する
パン屋開業にあたっては、資格取得やさまざまな手続きが必要になります。どのようなものがあるかを具体的に説明します。
食品衛生責任者
パン屋や飲食店など食品を扱う店舗で営業を行う場合、1店舗につきひとり「食品衛生責任者資格」を持つ人がいなければなりません。食品衛生責任者資格とは、食品衛生上の管理運営に当たる責任者をさします。食品衛生責任者資格を取得するには、自治体の食品衛生協会などが主催する食品衛生責任者養成講習会の受講が必要です。
菓子製造業許可
開業しようとしているパン屋が、パンの製造とテイクアウトでの販売を行う場合、この「菓子製造業許可」が必要となります。食パンなどは菓子ではないと考えてしまいますが、菓子パンだけでなく食パンやフランスパンなども法律上は「菓子」と分類されています。パン生地から作らずに生地を仕入れて焼き上げる場合でもこの許可は必要です。
飲食店営業許可
すべての飲食店舗において取得が必要となるのが「飲食店営業許可」であり、パン屋の場合もイートインだけで営業するのであればこの飲食店営業許可だけで問題ありません。
しかし、テイクアウトでの販売を行う場合は捉え方が二つあります。先に説明したように、菓子パンだけを販売する場合は菓子製造業許可の取得が必要であり、サンドイッチや焼きそばパンなどのようにパンを焼き上げたあとでなんらかの調理を加える場合は調理パンとみなされるため飲食店営業許可の取得が必要になるのです。つまり、開業を進めているパン屋が菓子パンも調理パンもテイクアウト販売するという場合には菓子製造業許可と飲食店営業許可の二つが必要ということになります。
食料品等販売業許可
「食料品等販売業許可」は、食料品を店内で販売するための許可です。この許可については、お店で調理パンを製造するのではなく、他の業者が製造した調理パンを店内で販売する場合に取得が必要ですが、自治体によって届け出が必要かどうかが異なるため、事前に保健所へ確認しましょう。この許可が必要となる場合、床や内装などに細かい基準が定められているため、物件を決める前に確認してみてください。
パン製造技能士
パン屋を開業するにあたって必須となる資格ではありませんが、持っておくことで有利となり得る資格が「パン製造技能士」です。パン製造技能士は国家資格のため、持っていることでパン製造におけるスキルを持っているという証拠となり、今後広告展開を考える際のキャッチコピーにすることもできます。
等級は特級・1級・2級に分かれており、受験するには2級の場合は実務経験2年以上または必要な学課の修了、1級の場合は実務経験7年以上、さらに特級は1級に合格したうえで実務経験5年以上と、長い年月が必要になります。国家資格であることからわかるように簡単に取得できるものではありませんが、中長期的な目標として検討してみるのも良いでしょう。
パン屋開業後に陥りがちな失敗と対策
- パン屋を開業した後の集客ができていない
- 体力がもたない
- 後継者がいない
初期費用の準備や必要な許可や手続きも順調に進んだものの、いざパン屋を開業してもうまくいかないと悩む人も少なくありません。どのような理由から失敗に至るのか、パン屋開業後に陥りがちな失敗例とその対策について紹介していきます。
パン屋を開業した後の集客ができていない
パン屋は競合が多いこともあり、差別化を明確にすることで集客を得られ、その結果安定的な経営につながります。そのため、最初の出店エリア設定やコンセプト作りの際のターゲット設定を間違えてしまうと集客を得られないという問題が生じてしまいます。特に未経験からの開業を考えている場合には、経営ノウハウやマニュアルが整っているフランチャイズ加盟での開業を検討してみることも必要でしょう。
また、開業後に集客を強化するための取り組みができているかも重要です。店舗の集客にはさまざまな方法がありますが、それぞれかかる費用やターゲットになる客層が異なるため、適した方法を選んで売上につなげていくことが大切です。
まずは、SNSなど無料で始められるサービスで情報をこまめに発信し、店舗の認知拡大や新規客に見つけてもらうきっかけを作るのがおすすめです。費用をしっかりかけられる場合は、店舗がある地域へのポスティングや折り込みチラシなどの広告を打ってみるのもよいでしょう。
パン屋の集客や広告についてさらに知りたい方は、こちらの記事もあわせてお読みください。
体力がもたない
少人数で経営を進める場合には、体力面が維持できず断念してしまうということも考えられます。そのため、出店エリアの生活時間帯を把握し、パン屋経営においてパートナーがいる場合にはお互いの健康を考慮したうえで営業時間や定休日の設定を明確にすることが重要です。
フランチャイズ加盟での開業の場合は、定休日や営業時間もはっきりと決まっている場合も多いため、体力面での不安や時間の自由度を考える場合には、独立ではなくフランチャイズ加盟での開業も選択肢に加えることも視野に入れておきましょう。
後継者がいない
規模の小さなパン屋において、自分自身や他のパン職人の味を売りにしている場合には、パン職人が体調不良で来られなくなるとお店が成り立たず、無理して出勤するということも起こり得ます。軽度の体調不良でも度重なれば大きな病気につながることも考えられるため、家族や従業員と出勤の調整をしつつ、後継者となりうるパン職人を募集するなど複数の手段をとってみると良いでしょう。
まとめ

今回は、パン屋を開業するにあたっての必要な費用や資格、開業までの一連の流れを紹介しました。パン食が一般的なものになっている現代では、パン屋の開業に対しても身近に感じるという人や「自分もやってみたい」と思う人が多いかもしれません。
しかしながら、パン屋開業はただ単にパンを焼くだけでなく、物件探しやコンセプト設定、開業費用の手配、メニュー開発、人材雇用など幅広い業務をこなさなくてはならず、すべてスムーズに進むわけではありません。資格取得や許可申請など煩雑なことも多く、開業後も安定的な運営に目を配らなくてはなりません。
それでも、自分の理想とするお店を実現できるパン屋の開業は、喜びややりがいに繋がる事が期待できます。パン屋開業が未経験であってもフランチャイズ加盟や開業支援サポートなどの手段があるので、情報をひとつひとつ精査しながら夢の実現に向けて踏み出してみてはいかがでしょうか。
記事のURLとタイトルをコピーする